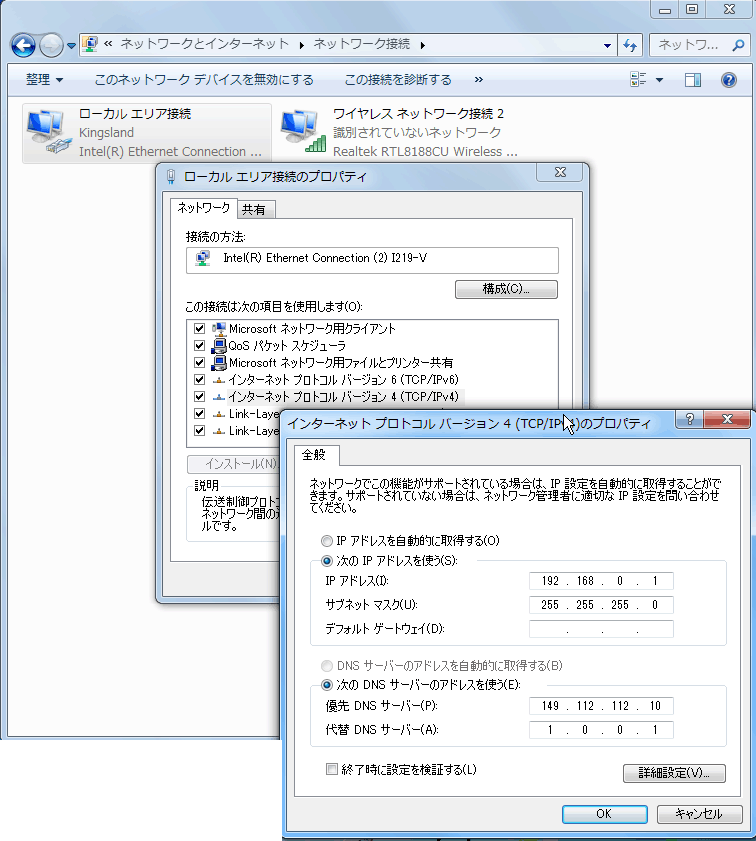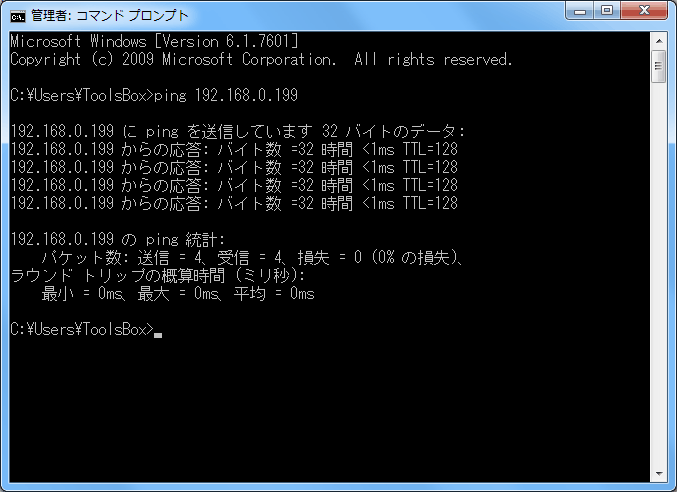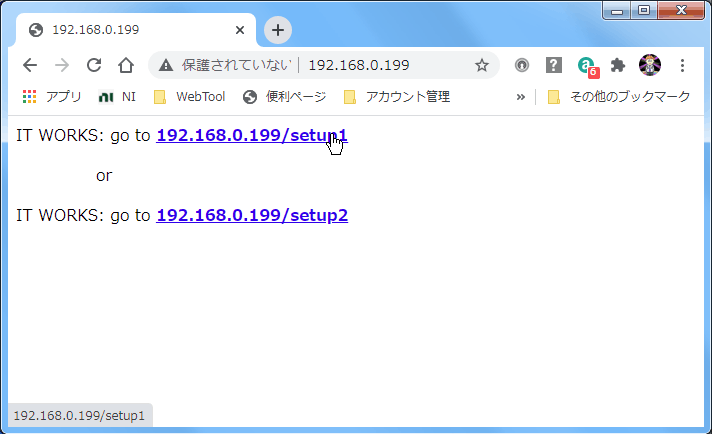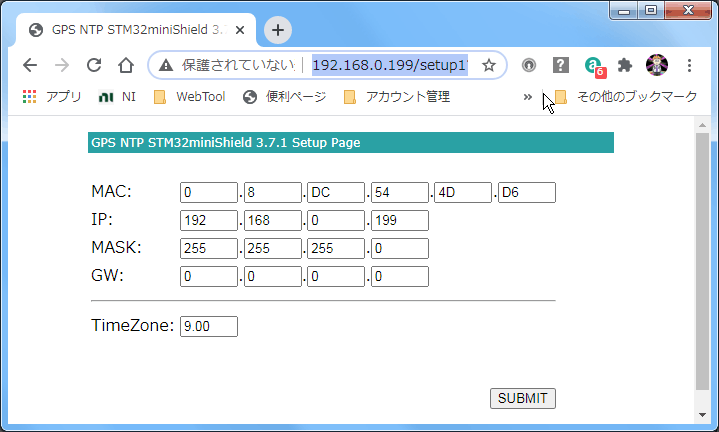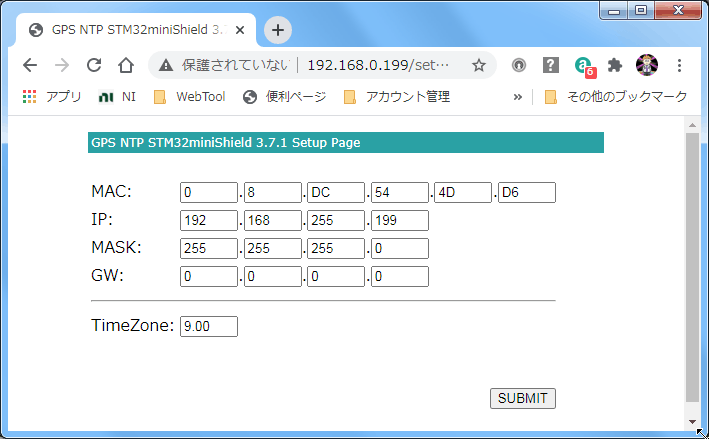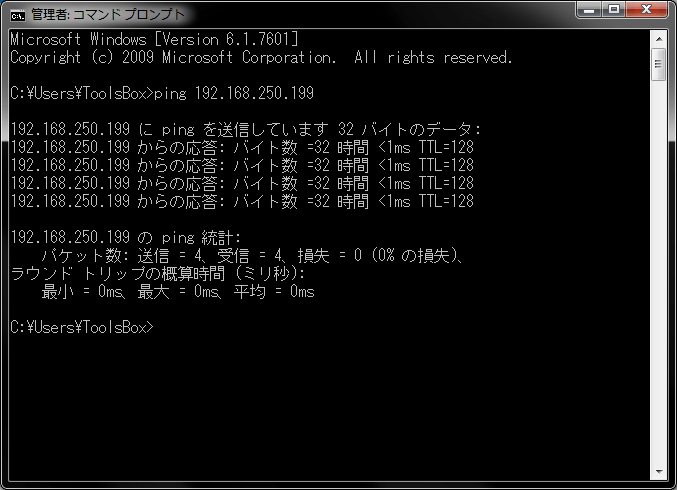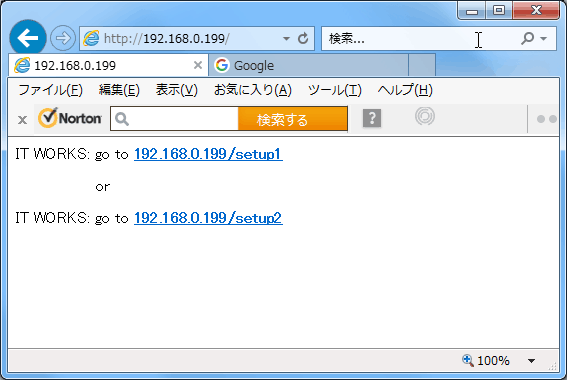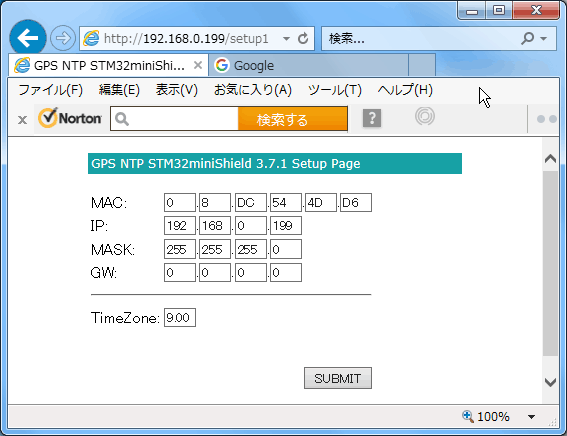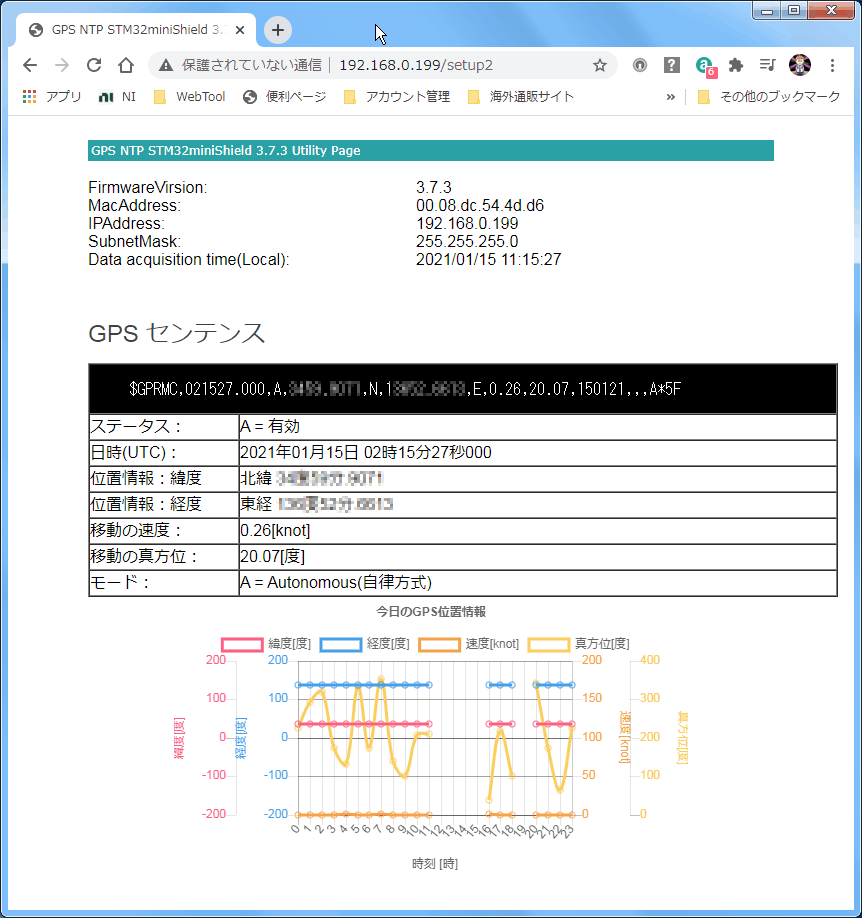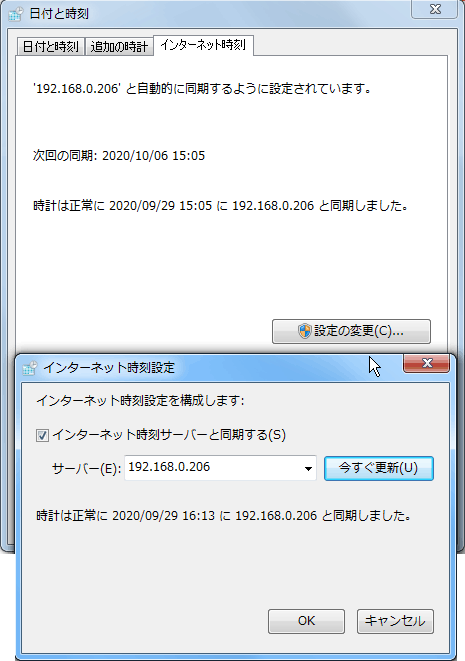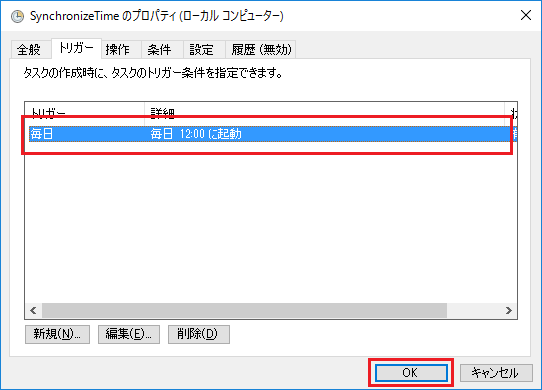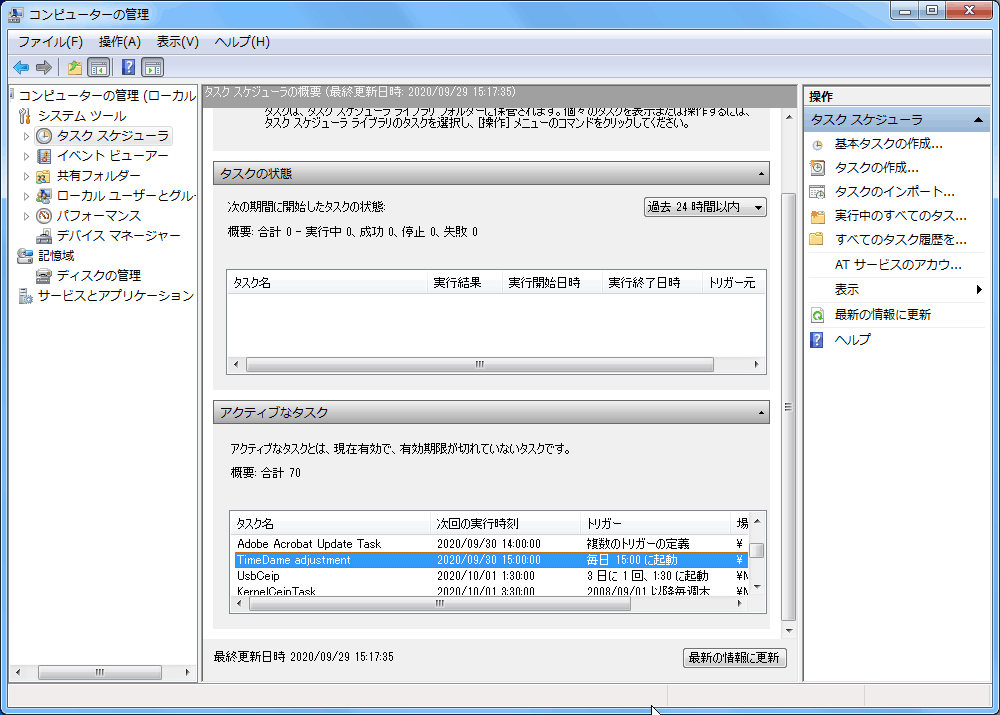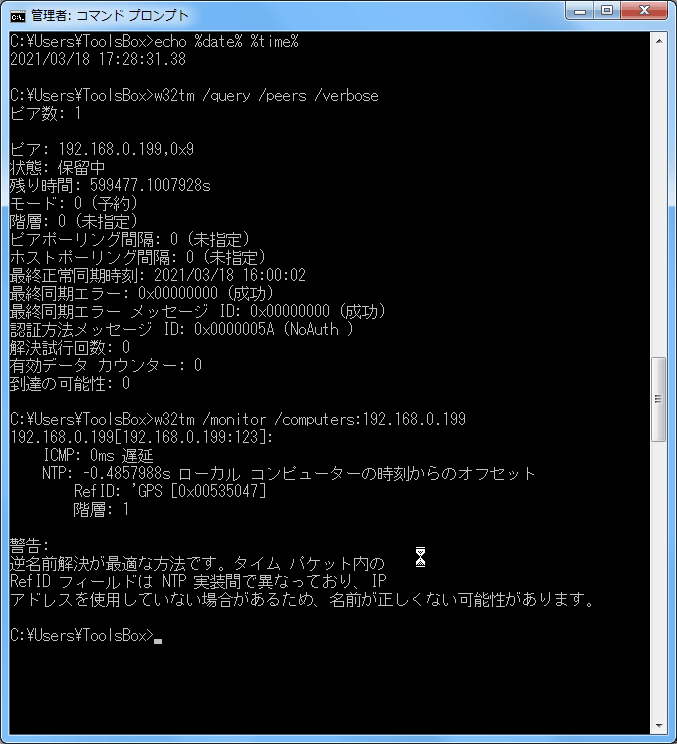最終更新日:2023年6月5日
作成日:2023年6月5日
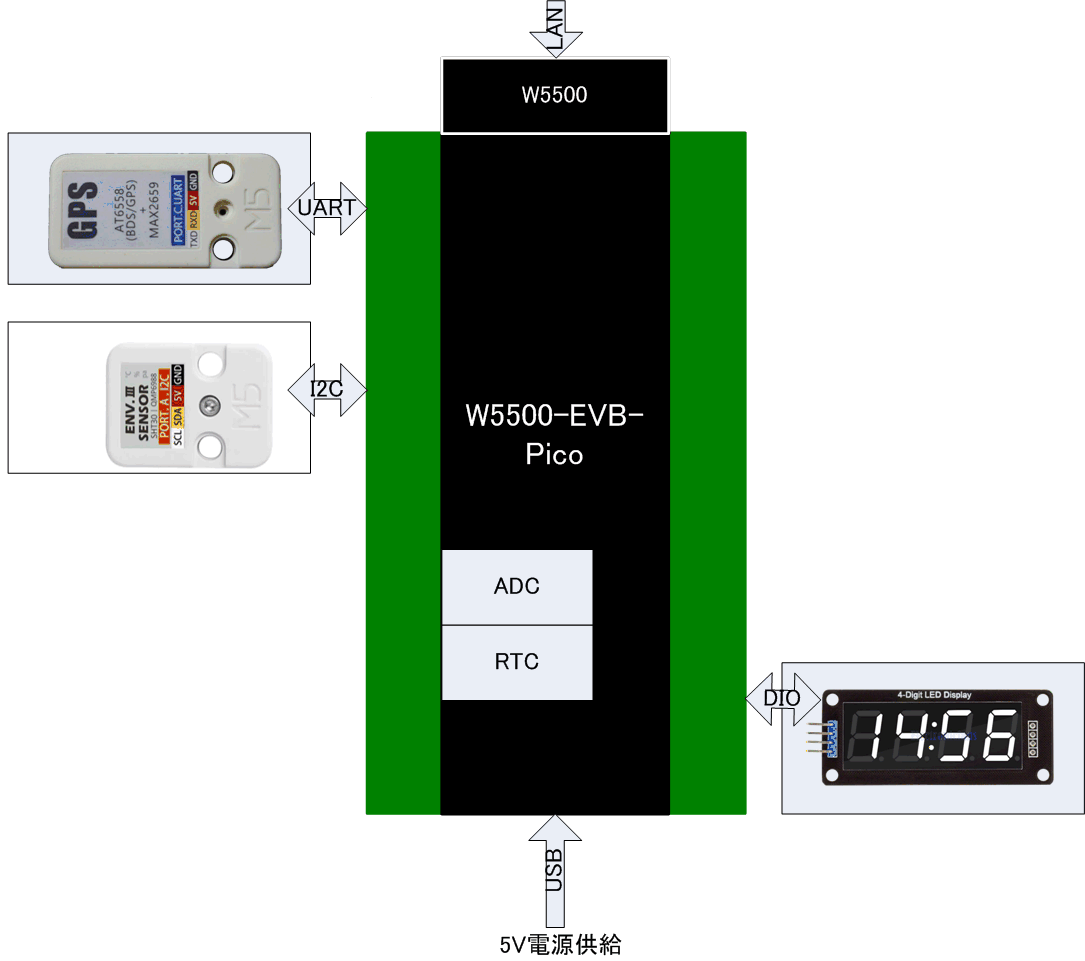
ここでは、W5500-EVB-PICO + Grove Shield for Pi Picoを使用した、提供可能なGPS NTP タイムサーバを紹介します。
- GPSモジュールはM5Stack社のGPSユニット(U032)を検討します。Grove Shield for Pi
Picoを使う事を検討したため、Groveコネクタ接続で使えるのは便利です。2mのGroveケーブルは市販されております。ラインバッファを噛ますことでケーブル長の延長は可能かと思います。
- 時刻表示はTM1637を搭載した7セグメントLED 4桁表示タイプを検討します。コロン付きのモノが時刻表示らしく見えるはずです。
|
|
備考 | ||
| 時刻修正方式 | GPS | センテンス$xxRMCを読み取って調整 | |
| 動作状態 |
SNTPサーバ(時刻同期) HTTPサーバ(設定) |
||
| 時刻精度 | GPSモジュールの精度に準ずる | 内部時間は処理時間分の遅れあり | |
| LANインターフェース | 10/100BASE-TX | RJ-45 | |
| 対応プロトコル | SNTPv4 | ||
| 外形寸法(mm) | |||
| 電源電圧(V) |
DC5V 消費電流210mA(実測値) |
USBマイクロBで提供 ACアダプタは100−240VAC50/60Hz |
|
| GPSアンテナ | 感度 |
Tracking: -162dBm Capture: -148dBm Cold start: -146dBm |
|
| 外形寸法(mm) | 48*24*8mm | ||
| ケーブル長(m) | Groveケーブルによる | ||
| 固定方法 | LEGOと同じサイズの穴 × 2 | ||
|