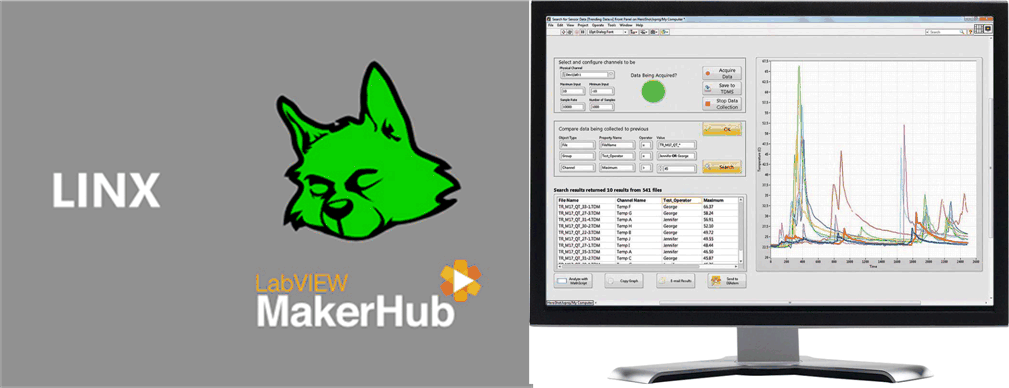
最終更新日:2017/2/6
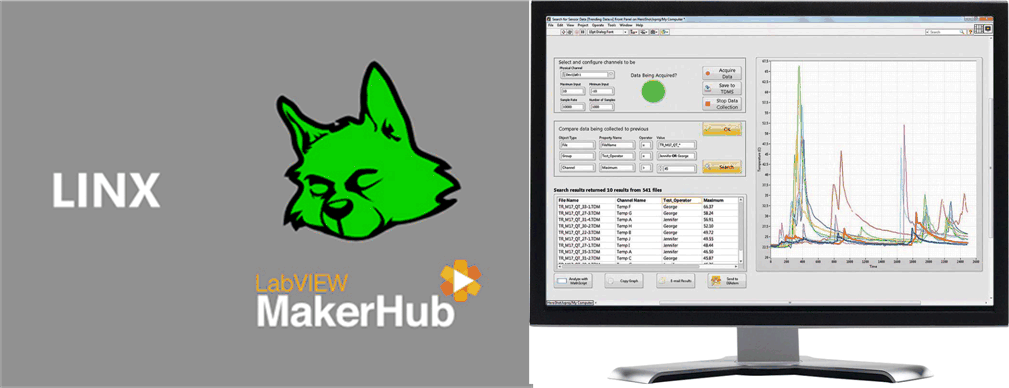
LINKは LabVIEW MakerHub という団体が提供する 一般的な組込プラットフォームとの接続インタフェース です。
LIFAのサポートをNIが止めLINKへ移行すると明言しています。ただ、サポートはNIではなく LabVIEW MakerHub です。https://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ja/nid/212478
VIPMを介して開発環境にライブラリをインストールします。最新版は3.0.1.
対応ターゲットはUpdate毎に増えているようです。把握しているデバイスをリストアップします。
- Arduino
Arduino LLC および Arduino SRL が設計・製造を行い、登録商標を持っているデバイス或いは統合開発環境です。
オープンなプロジェクトのため互換機がたくさん存在します。
互換機だとUSB-URAT変換のところで動かなかったり、IOデバイスpin互換がなく動かない場合もあるようです。
LIFAからLINXへ移行するようNIも勧めています。- chipKIT
ArduinoがAVRチップを使用することに対して、PIC32を使用してArduino互換ボードを構成し提供しています。
PIC32についてはクレア工房 殿のサイトが詳しいです。https://www.clarestudio.org/elec/pic32/
8bitマイコンなのですが、これまでイメージしているPICとは別物でAVRと同じ仕組みのようです。
敢えてこのデバイスを使う意味合いを見いだせていません。- myRIO
NIが提供するCortex-A9+Xilinx FPGA I/Oの教育用デバイスです。
教育用なので入手に関しては制限があるようです。そこそこRICHな仕様ですが\ 132,000ですし、開発環境もそこそこ整備が必要です。- BeagleBone Black
LINXver3.0からサポートされているデバイスです。
TIのCortex A8 ARMのプロセッサーを搭載したBeagleBoard.org(米)開発販売のボードです。基本Linuxを動作させます。- Raspberry Pi 2(RPI2)
Raspberry Pi 3(RPI3)
イギリスのラズベリーパイ財団(英語版)によって開発されたシングルボードコンピュータでBroadcom社のARMプロセッサを搭載している。
搭載できるOSは専用のRaspbian以外にも亜種のOSがたくさんあります。Windos10IoTもサポート計画しているとのことです。
ボードの構成によって進化しておりRPI/RPI2/RPI3・・と遷移しています。RPI3で$35という価格は魅力的です。MIPS値も800MIPS(ARM Cortex A8/400MHz)でArduinoUNO(16 MIPS)と比べても桁違いです。
消費電力7Wをどう見るかというところもありますが。
【LINX環境整備】
手元のLabVIEW2016の環境にLINXを入れてみましたが、これは使える機能が限定されてしまいます。
LabVIEW Home Bundleを入手し、専用の環境を構築した方が得策のようです。
- LabVIEW Home Bundleのインストール
- NI-VISA16のインストール※LabVIEW Home Bundleないのものではなく最新版の方がいいです。
- LabVIEW Control Design and Simulation Module 2014のインストール※折角のライセンスなので
- LabVIEW MathScript RT Module 2014のインストール※折角のライセンスなので
- VIPM2016SP1のインストール※LabVIEW Home Bundleないのものではなく最新版の方がいいです。
- LINX最新版のインストール※VIPM経由
- ArduinoIDEのダウンロード/インストール
| MakerHubの設定をします。ArduinoをUSBで接続しておきます。これ以前にデバイスドライバ等がインストールされている必要があります。 |
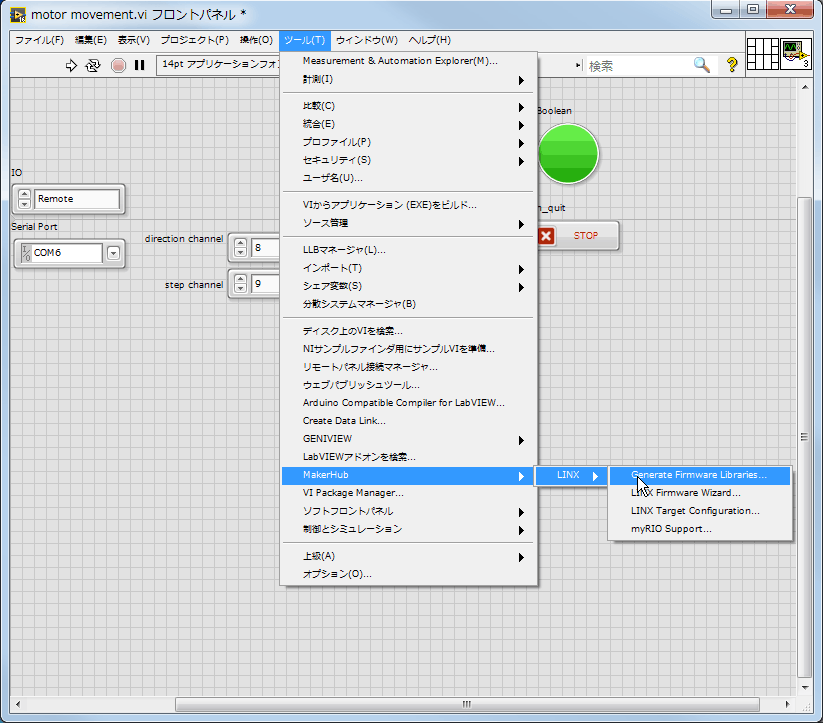
|
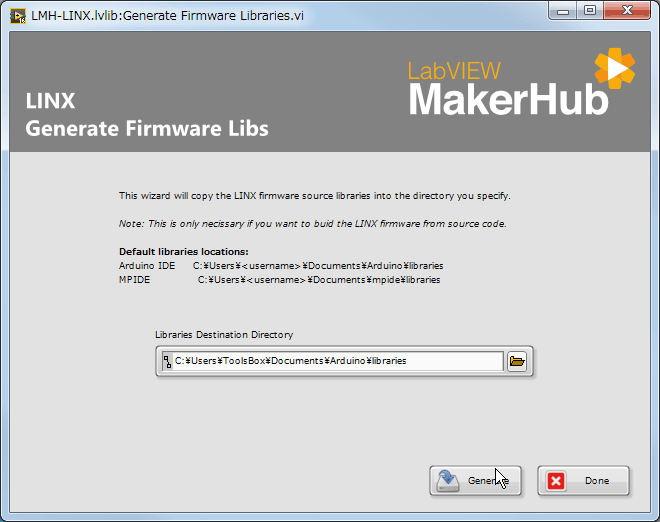
|
| 指定されたパスにライブラリを構築します。 |
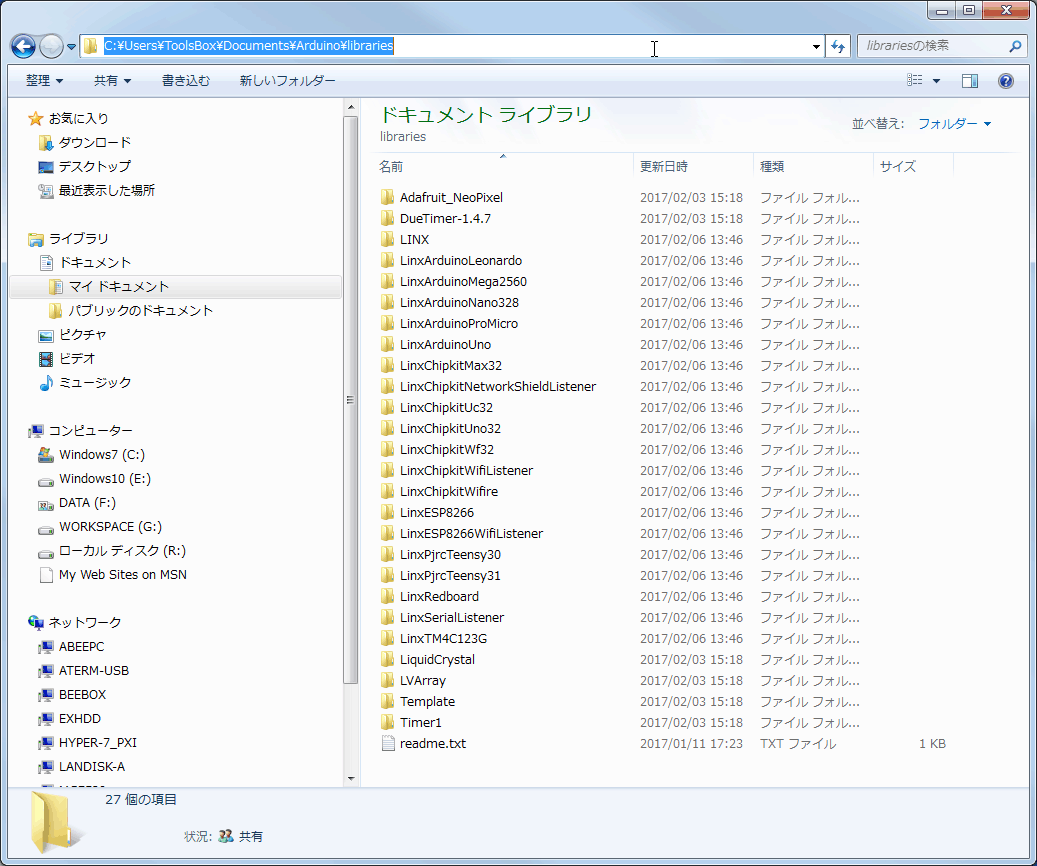
|
| 実際に構築されたライブラリを確認しました。結構な量を書き出しています。 |
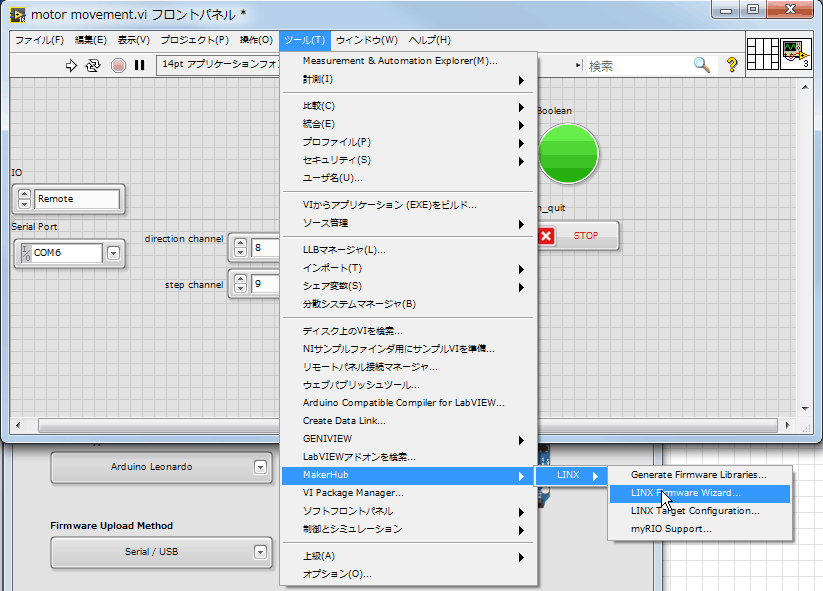
|
| 続いてファームウエアの設定をします。 |
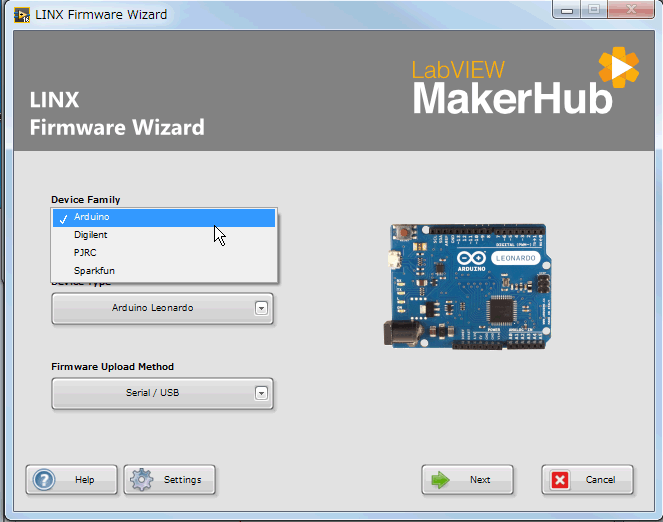
|
| ここで接続されているデバイスの種類/実際のデバイス/接続方式とドライバを選択します。 |
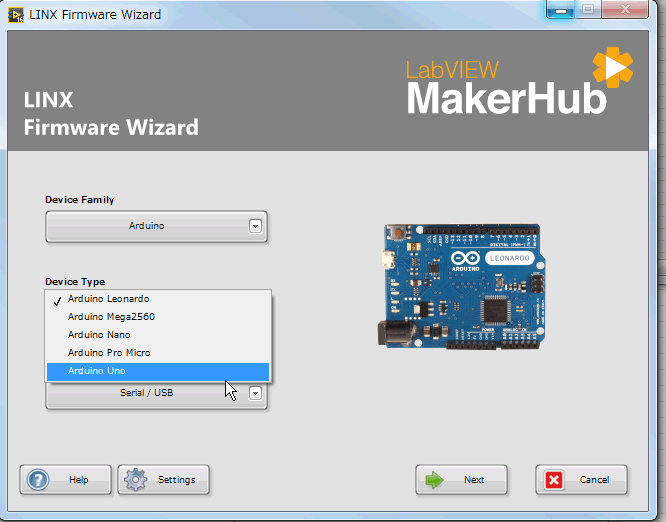
|
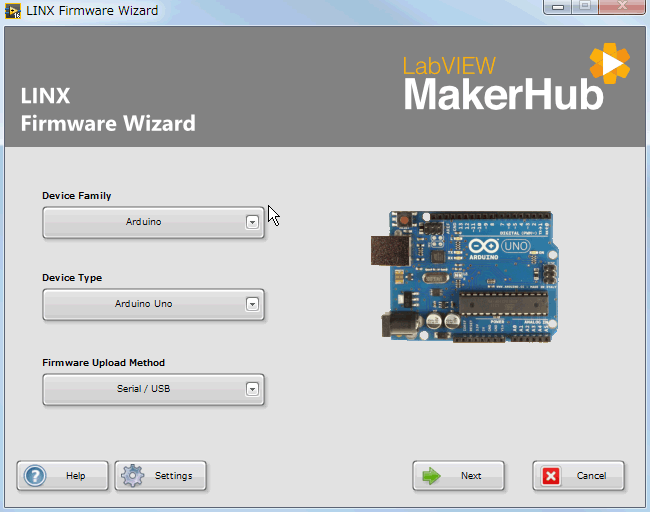
|
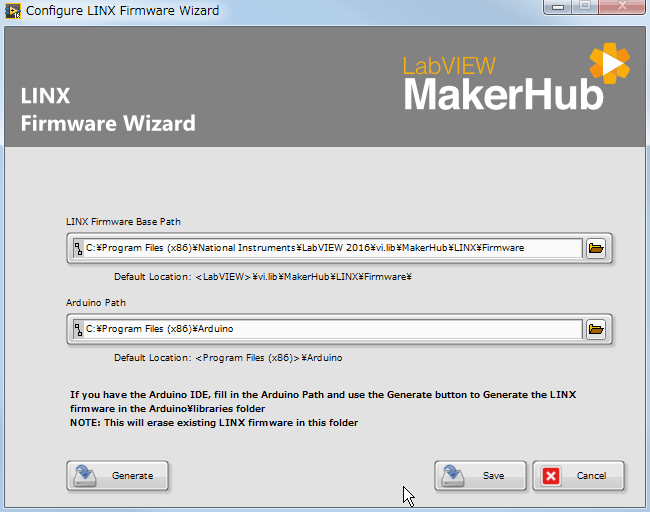
|
|
Settingを押してFirmwareのパスを設定します。ここを見る限りArduinoIDEを予めインストールして おかないといけないことが判ります。 |
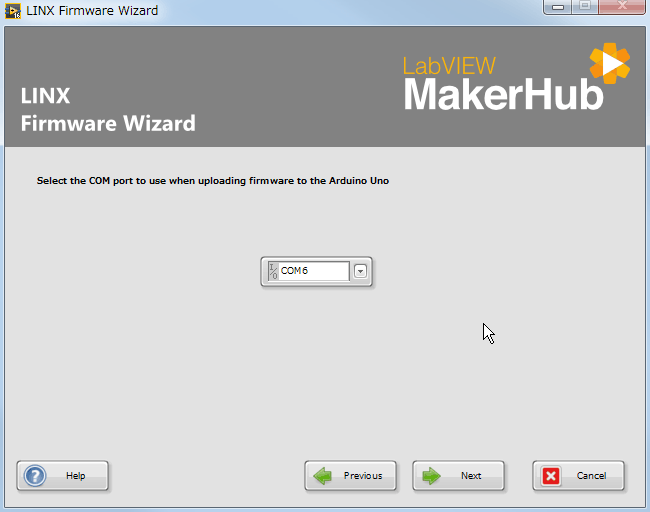
|
| ファームウエアをダウンロードするためポートを指定します。 |
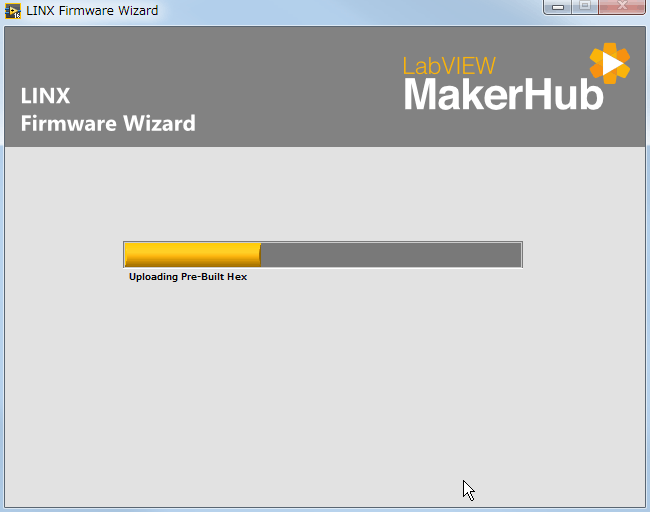
|
| 事前に作成済みのファームを落とすか改めてbuildしてファームを落とすかを選択して実行します |
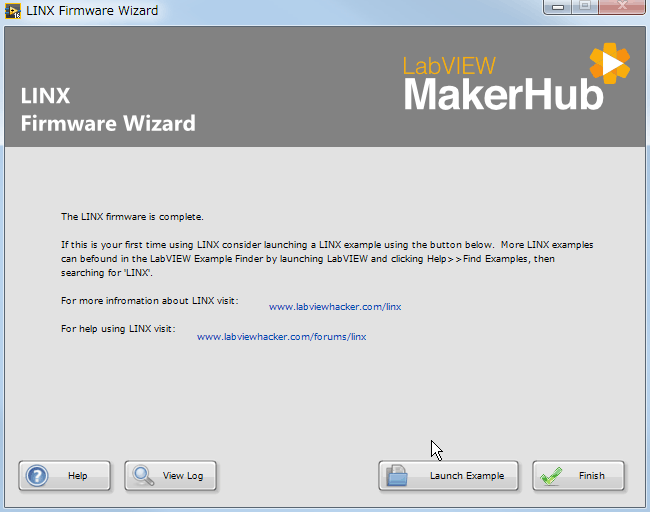
|
| きちんと落ちるとここでExampleを開いて動作確認が出来ます。Lチカのサンプルです。 |
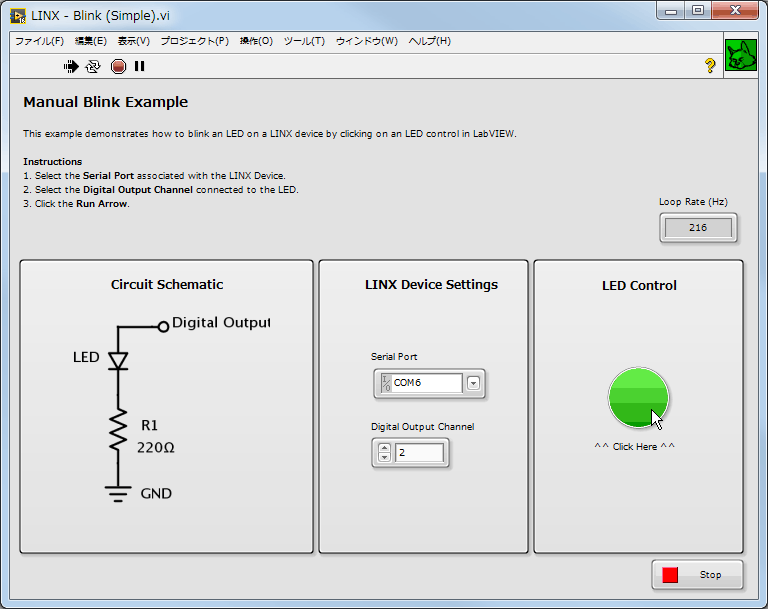
|
|
動きとしては、LINX用のファームを都度落として、通信してLEDの点滅を実現するというようなものです。 反応も遅いですし、LoopRateからして5msec掛かっていることが判ります。これを見る限り、『Arduino Compatible Compiler for LabVIEW』の方が興味深いです。 |
| LINXはRasberyPiターゲットで試し直すとして、Arduinoでは余り意味がないという印象を持ちました |
【LINXのExample紹介】
Exampleの数は明らかにLIFAより多いです。基本的に相当する機能のExampleは用意されています。ただ、コンパイラでBuildしてダウンロードするという仕組みはないようです。Local/Remoteという選択肢があるのですが、この辺りが明確に理解できていないのが正直なところです。
もしかしたらLocal設定はLV2014でないとだめなのかもしれません。【実際に使ってみて】
とりあえず手元にArduinoUNO互換機があるのでExampleを動かしてみました。
アナログ入力の確認もしてみましたが、LIFAの方が結果が良いように思います。
Firmwareの比較が出来ないのでさてどうしたものかやっぱりLINXを使うならターゲットはRasberyPiなのかと思います。こちらはライセンスフィーが発生しないので、LV2014環境を構築してから再度検証したいと思います。それまでにRasberyPi3も入手したいところです。
【関連書籍紹介】
『LabVIEW Home Bundle』なり『LabVIEW MakerHub』に掛かる関連図書を検索しましたが現状は見当たりません。
ハードウエアを伴った紹介本が出ていてもおかしくはないのですが。。。【余談】
Exampleでの動作確認中LabVIEW2014を要求されました。LINXを使う環境はLabVIEW2014英語版に固定した方が良さそうです。この場合、ライセンスはLabVIEW Home Bundleなるエディションを購入して構築した方がよいように思えました。
$50でライセンス取得出来るようですが、日本で購入するのであれば秋月電子が安価のようです。
| 販売店 | 価格 | 備考 |
| 秋月電子 | \5800(税込) |
送料\500 代引き手数料\300 |
| DegiKey | \5,958 | 消費税は別であり、送料の扱いも注意が必要です |
| スイッチサイエンス | −− | SparkFun Inventor's Kit for LabVIEWの取り寄せ扱いのみです |
| アマゾン | from $49.99 + $5.12 shipping | 日本のアマゾンでは扱っていないようです。 |
免責事項
本ソフトウエアは、あなたに対して何も保証しません。本ソフトウエアの関係者(他の利用者も含む)は、あなたに対して一切責任を負いません。
あなたが、本ソフトウエアを利用(コンパイル後の再利用など全てを含む)する場合は、自己責任で行う必要があります。本ソフトウエアの著作権はToolsBoxに帰属します。
本ソフトウエアをご利用の結果生じた損害について、ToolsBoxは一切責任を負いません。
ToolsBoxはコンテンツとして提供する全ての文章、画像等について、内容の合法性・正確性・安全性等、において最善の注意をし、作成していますが、保証するものではありません。
ToolsBoxはリンクをしている外部サイトについては、何ら保証しません。
ToolsBoxは事前の予告無く、本ソフトウエアの開発・提供を中止する可能性があります。
商標・登録商標