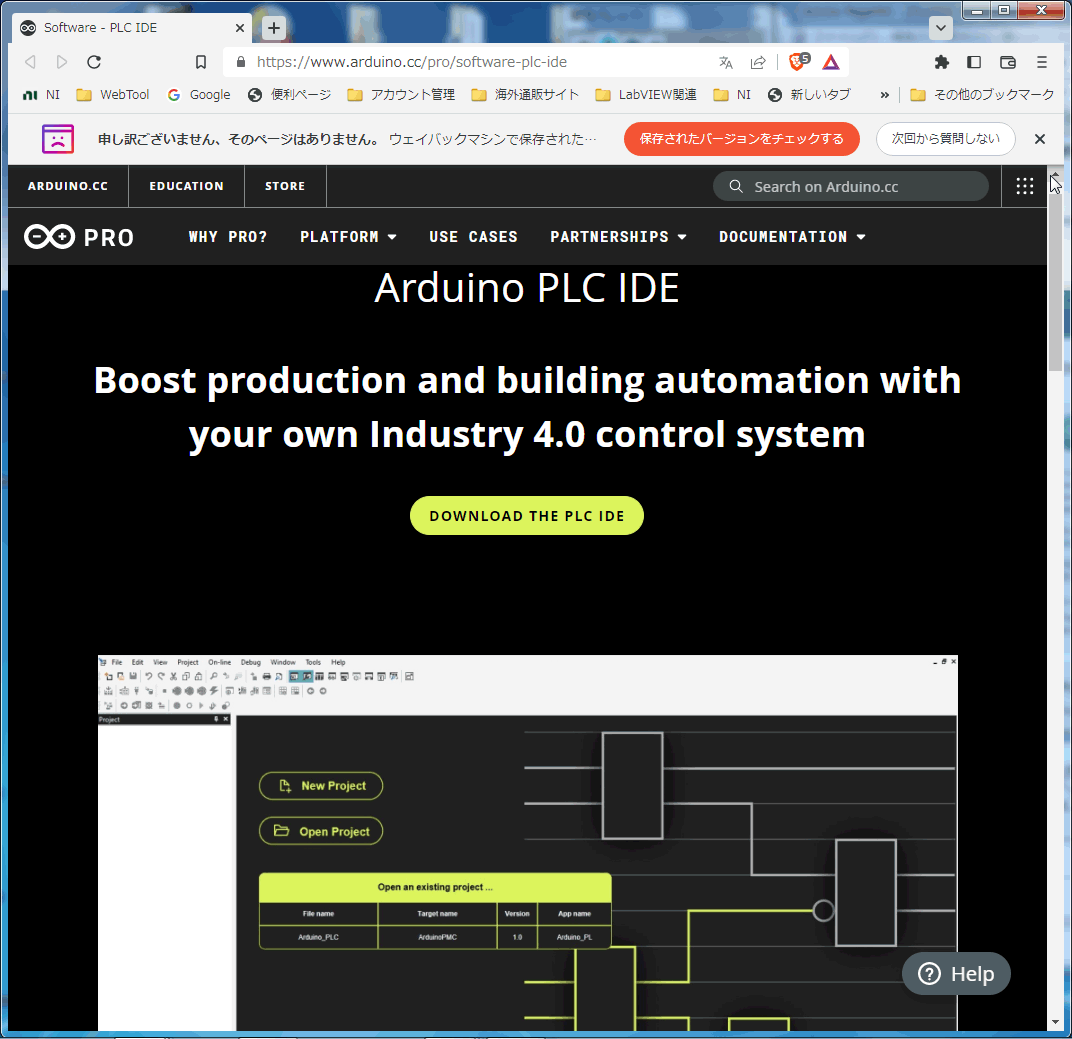
最終更新日 2022年12月22日
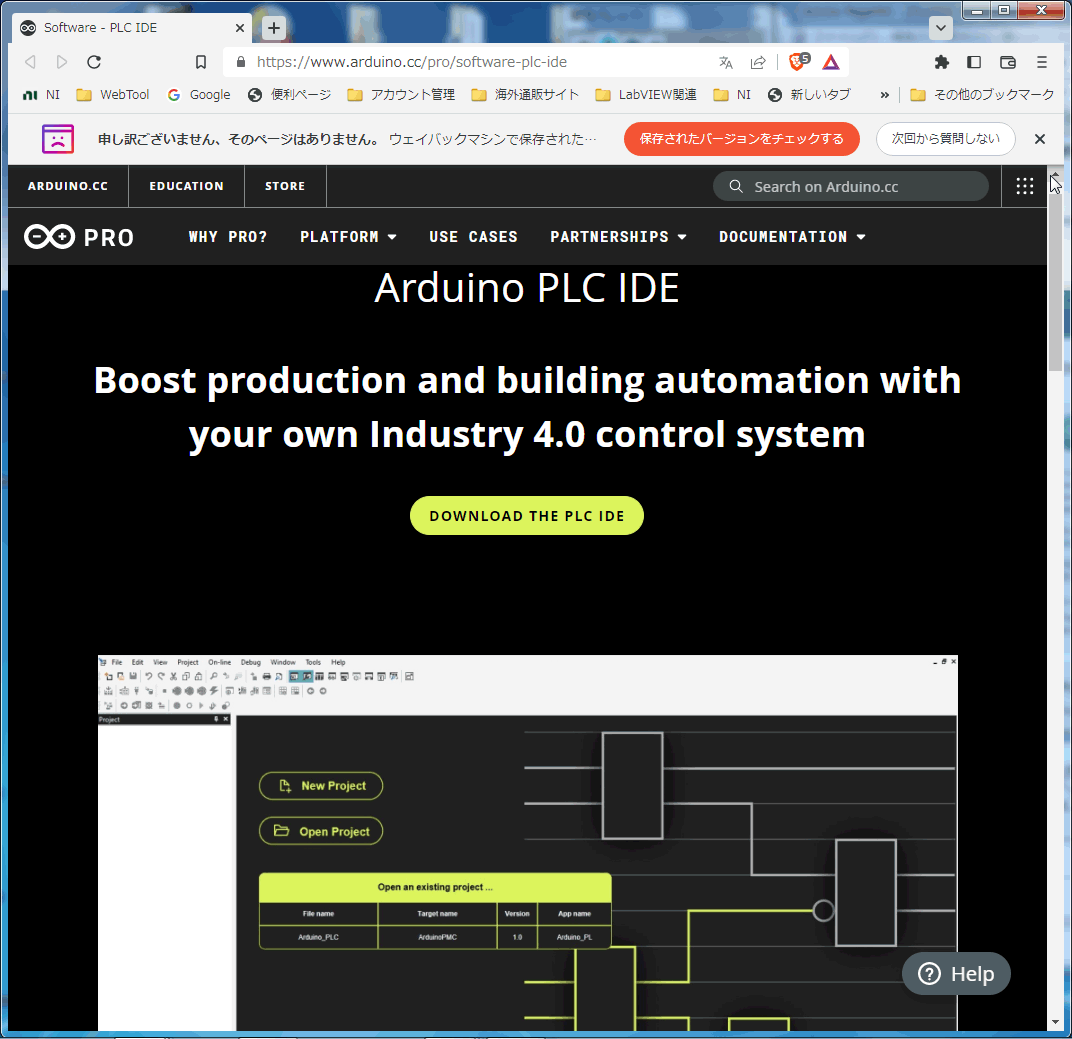
Arduino PLC IDEなるモノがリリースされていることが判りました。迂闊でした。
「IEC 61131-3標準言語を使用してプログラムできる」とあるのですが、ピンと来ません。ラダー線図とは異なるのでしょうか?そこからの調査が必要なことが判りました。IEC 61131-3プログラミング言語
MONOistの過去記事にオムロン社員の方の記事がありました。PLCの国際標準プログラミング入門として6つほどリリースされているようです。参考にしました。
- PLCの国際標準プログラミング入門(1):IEC 61131-3とPLCopenの目的とは
- PLCの国際標準プログラミング入門(2):IEC 61131-3の特長〔前編〕5つのプログラミング言語と変数
- PLCの国際標準プログラミング入門(3):IEC 61131-3の特長〔後編〕プログラムのモジュール化
- PLCの国際標準プログラミング入門(4):PLCopenの「Motion Control FB」とは
- PLCの国際標準プログラミング入門(5):PLCopenの「Safety FB」とは
- PLCの国際標準プログラミング入門(6):IEC 61131-3の最新技術動向とJIS B 3503
1993年にPLCのプログラミング言語の国際規格「IEC 61131-3」が発行されたとの事。背景として、欧州を中心に「ハードウェアについてはメーカーの独自性を尊重するが、プログラミング言語は統一しよう」という動きが反映されているようです。
「IEC 61131-3」は従来主体だったラダー言語を含む「4言語+1要素」を規定しているとのことです。
日本でも公共建築工事標準仕様書でJIS B 3501(一般情報)、JIS B 3502(装置への要求事項及び試験)、JIS B 3503(プログラミング言語)B3503準拠のプログラマブルコントローラが指定されていますので重要です。この記事では2013年時点の状況を踏まえています。欧米ではIEC 61131-3準拠がほぼ100%なのに対し、日本では半分以上が「ラダー言語主体」の従来型プログラミングツールを使っていると記しています。この部分が、Arduino PLC に踏み込めない所なのかと思います。どうしても大手のPLCメーカ依存開発環境を使う事になりうる要因かと思います。実際自分もomron、symac環境での案件とか、三菱melsec環境案件、キーエンスkv環境案件と案件企業ごとにグループ分け出来ます。
この記事では続いて、「円高の影響を受け変わりつつある」としているのですが、2022年までにArduino PLC案件はありません。部分部分でArduino PLC案件があってもいいように思うのですが。
その意味でModbusTCPスレーブデバイスをArduinoで構築して組み込んでゆく等努力も有りだなと思う次第です。「IEC 61131-3」は“PLCアプリケーションの開発効率化”を目的としています。その為Sysmacだったりするとアドレス自体が目的によって割り当てられていますが、「IEC 61131-3」では外部IOは固定アドレスですが、内部変数は名前付けによる自動アドレス割付で、一種の隠匿となります。
|
|
IEC 61131-3 |
|||
|
|
①変数(信号名) | ②変数の型 | ③アドレス | |
| 一般メモリ | M100 | 運転準備 | BOOL | 自動割付 |
| D0 | 風量 | DWORD | 自動割付 | |
| D10 | 運転日 | DATE | 自動割付 | |
| 保持メモリ | D100 | 累積運転時間 | TIME | 自動割付 |
| デジタル入力 | X00 | ファン始動 | BOOL | %IX1.0.0 |
| デジタル出力 | Y01 | ファンモータ | BOOL | %QX2.0.0 |
| アナログ出力 | D1000 | 風量 | INT | %QW3.0 |
窓の社に「PLC IDE 1.0」の紹介記事がありました。初物ですし、とても参考になります。
ArduinoPLCIDEをインストールして見ました。バージョンは1.0.0.0_20221205です。
- Windows10以降対象となっていますが、Windows7SP1x64環境にも普通にインストール出来、PC再起動後IDE起動出来ました。
- デフォルトの言語環境は英語のようです。Optionを起動すると言語メニューがありましたが、英語/中国語/イタリア語の三者一択でした、中国語がサポートされていることから日本語対応も近々に行われるのでは無いでしょうか?
- ターゲットデバイスとしてArduinoは「Arduino Opta」というデバイスがリリースされたようです。Opta Lite(SKU: AFX00003)で$146.40となっています。
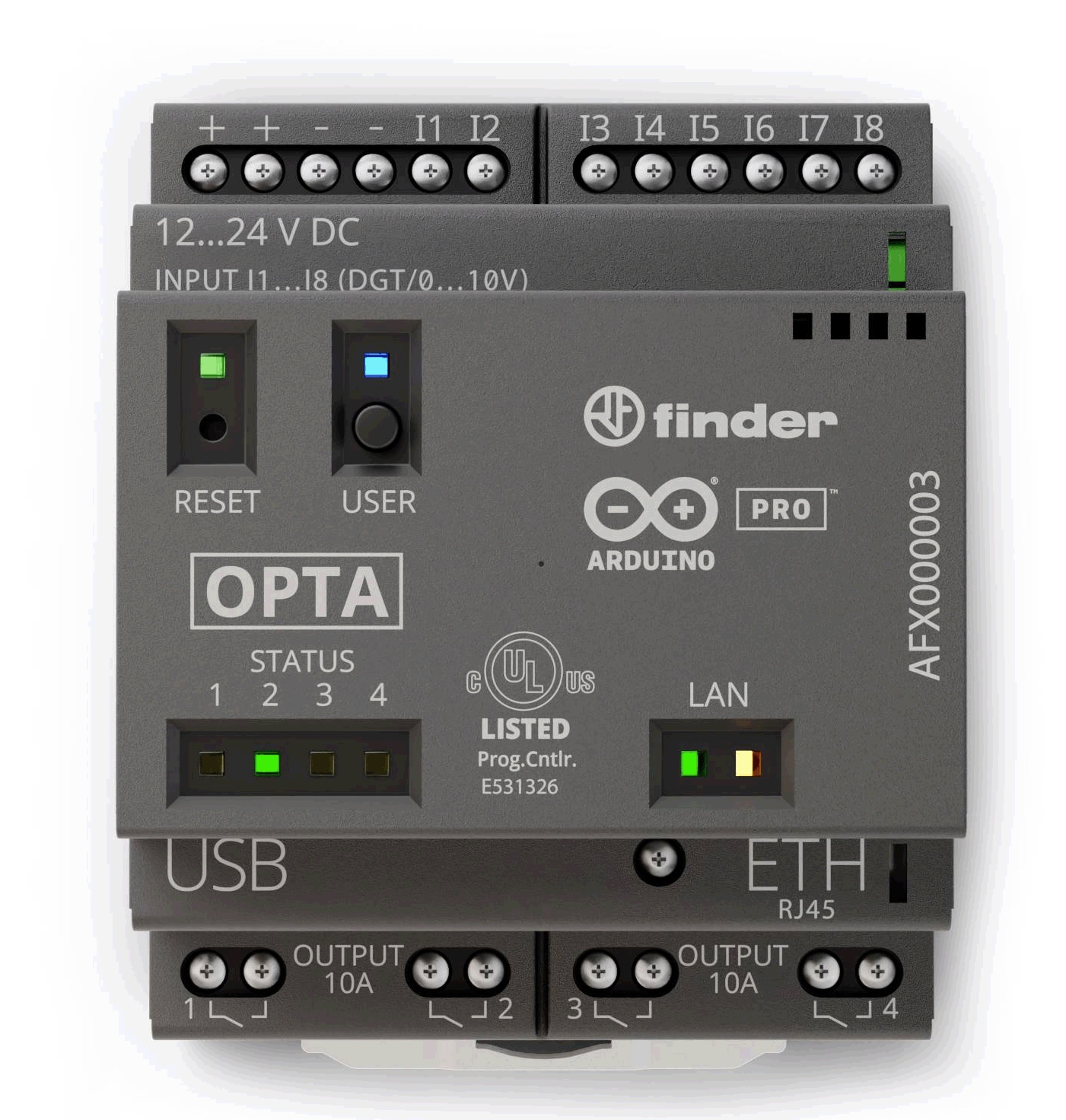
- 簡単な仕様は入手出来ましたが、搭載CPUがなんなのかとか云った情報はどこにあるのか?
No. of inputs (max.) 8 No. of relay outputs (max.) 4 IP rating IP20 Interfaces USB-C、Ethernet Manufacturer part # AFX00003 Type Opta Lite Operating voltage 12 V DC, 24 V DC Max. ambient temperature +55℃ Min. ambient temperature -20 ℃ Product type PLC communication module
※ありました。--->
CPUは STM32H747xI/G とのこと とても興味が湧きました。そこそこのスペックです。
Flash:16MB
RAM:1MB
Board SKUs Arduino Opta Lite AFX00003 Microcontroller ID STM32H747XI Dual ARM Cortex-M7 core up to 480 MHz Cortex-M4 core up to 240 MHz Input Configurable digital / analog (0-10V) input 8 Actuators Relays
(250 V AC - 10 A)4 Connectivity USB Programming Port Yes Ethernet TCP/IP Yes ModBus TCP Yes Power Input voltage 12-24V DC Output relay rated voltage 250V AC Output relay maximum switching voltage 400V AC Memory SDRAM 1 MB Onboard flash memory 2MB internal + 16MB Flash QSPI Dimensions Weight 210g Width/Length/Height 69 /80 /90mm IP Protection IP20 RTC ~10days, NTP sync through ethernet Secure element ATECC608B Programming Arduino programming language Via Arduino IDEs, Arduino CLI, Arduino Web Editor IEC-61131-3 as option Ladder Diagram (LD),
Function Block Diagram (FBD),
Sequential Function Chart (SFC),
Structured Text (ST),
Instruction List (IL)実際にターゲットデバイスを入手して使ってみたいですね。また、既存のサードパーティデバイスがサポートされていないのか気になるところです。ただ、CPUスペックが可成り高いのでサポートされていないのでしょうね。
免責事項
本ソフトウエアは、あなたに対して何も保証しません。本ソフトウエアの関係者(他の利用者も含む)は、あなたに対して一切責任を負いません。
あなたが、本ソフトウエアを利用(コンパイル後の再利用など全てを含む)する場合は、自己責任で行う必要があります。本ソフトウエアの著作権はToolsBoxに帰属します。
本ソフトウエアをご利用の結果生じた損害について、ToolsBoxは一切責任を負いません。
ToolsBoxはコンテンツとして提供する全ての文章、画像等について、内容の合法性・正確性・安全性等、において最善の注意をし、作成していますが、保証するものではありません。
ToolsBoxはリンクをしている外部サイトについては、何ら保証しません。
ToolsBoxは事前の予告無く、本ソフトウエアの開発・提供を中止する可能性があります。
商標・登録商標
Microsoft、Windows、WindowsNTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Windows Vista、Windows XPは、米国Microsoft Corporation.の商品名称です。
LabVIEW、National Instruments、NI、ni.comはNational Instrumentsの登録商標です。
I2Cは、NXP Semiconductors社の登録商標です。
その他の企業名ならびに製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。